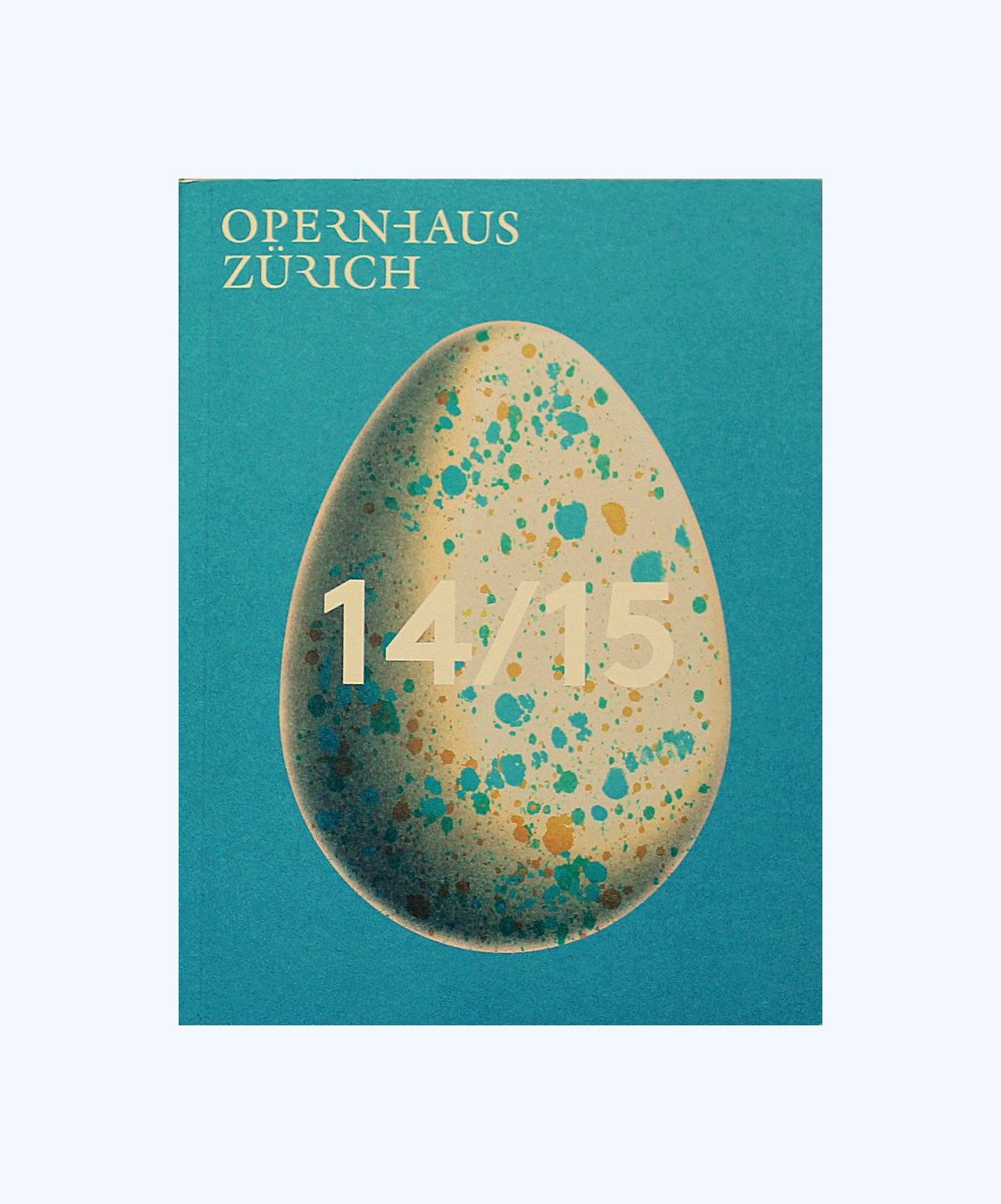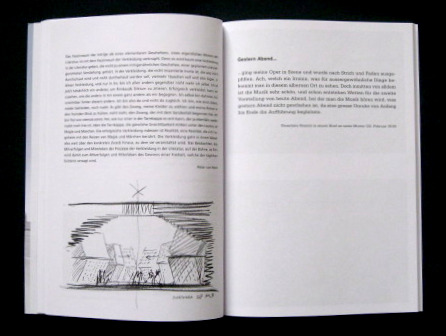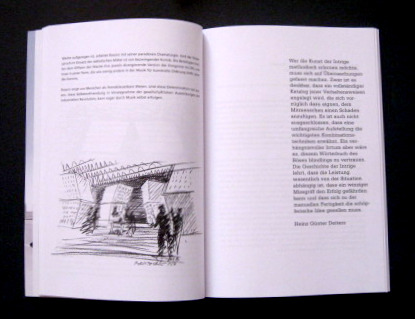秋までの休演の間、チューリッヒ歌劇場には大がかりな梯子が組まれていた。外壁は日に日に磨かれ、天に向けて両手を差し出す女神も天使たちも、今は真っ白に輝いている。
2015/ 16年のプルミエは、アルバン・ベルグの「ヴォツェック Wozzeck」で幕を開けた。19世紀初め、ドイツのライプツィヒで実際に起きた殺人事件をもとに創作されたカール・ゲオルク・ビューヒナーの戯曲。下 級兵士ヴォツェックを演じるのは、クリスチャン・ゲルハーヘル。幻覚の世界で奇矯な声に誘われながら精神に異常をきたし、ついには情婦マリーを刺殺する。
この作品を初め、オペラのプルミエは、幻想、幻覚、狂気の世界を彷徨するプログラムにフォーカスした企画が並び、その特化した視点は、精神医学の歴史に重要な役割を果たしてきたドイツ語圏スイスらしくもあり、かなりユニークだ。
例えば、ヴェルディのオペラ、「マクベスMacbeth」。権力と敵意に翻弄され、暗雲に覆われた世界を生きるマクベス夫人も精神を病んでいく。演出は、バリー・コスキー。
アンドレアス・ホモキ演出、ベッリー二の「清教徒」では、司令官の娘エルヴィーラが、婚約者に去られ発狂してしまう。オペラのハイライトは、あまりにも有名な「狂乱の場」。南アフリカ出身のプリティ・イェンデのソプラノが楽しみだ。
2016年1月。現代音楽の天才ヴォルフガング・リームのオペラ「ハムレット・マシーンDie Hamletmaschine」が登場する。
バレエのプルミエでは、ネザーランド・ダンス・シアター NDT を世界的なカンパニーへと育て上げたイジー・キリアーンの「神々と犬たちGods and Dogs」が、ウィリアム・フォーサイス振り付けの「In the Middle, Somewhat Elevated」とオハッド・ナハリンの「Minus 16」との3ステージで上演される。
アメリカン・バレエ・シアターで上演された映像を観た方も少なくないと思うが、アレクセイ・ラトマンスキ―が振り付ける、チャイコフスキーの「白鳥の湖 Schwanensee」の上演は、2月。
上の写真左から、アンドレアス・ホモキ、コマーシャル・ディレクターのクリスチャン・ベルナー、ファビオ・ルイージ、クリスチャン・シュプック。
安定した人気の高い演目の間に、チャレンジングな作品をきら星のように散りばめたカレンダー。いかにもチューリッヒらしい斬新さと洗練されたモダニズムで構成され、ヨーロッパの名門歌劇場にふさわしい、期待の大きいシーズンになりそうだ。
コメントを残す
チューリッヒ歌劇場の来年度のプログラムが発表されている。アンドレアス・ホモキ3期目のリードとなるが、プルミエは、オペラ10本、バレエは3本を核に構成された。
幕開けは、9月21日。ホモキ演出による、ワーグナーの「ローエングリン」。
11月には、日本でも人気の高いウィリー・デッカーの演出で、ベンジャミン・ブリテンの「ネジの回転 The turn of the screw 」が登場する。チューリッヒで半世紀ほど前に上演されたことがあるらしいが、珍しい演目だ。
クリスマスシーズンから新年にかけては、このシーズンにふさわしくモーツァルト最晩年の傑作「魔笛」を上演。ドイツのマインツ歌劇場のタチヤナ・ギュルバカが演出する。
バレエは、10月にクリスチャン・シュプック振り付けの「アンナ・カレーニナ」で幕を開ける。
1月。エドワード・クルグ、ウィリアム・フォーサイス、クリスチャン・シュプックの3人の振り付けで、「STRINGS」を上演。
バレエのプルミエ3作目は、「ジゼル」。大御所パトリス・バールの振り付けによる。
上の写真左から、ファビオ・ルイージ、アンドレアス・ホモキ、クリスチャン・シュプック。その隣りは、コマーシャル・ディレクターのクリスチャン・ベルナー。
シーズンを通して俯瞰すると、人気の高いオペラの数々を再演しながらますます挑戦的なプレゼンテーションをしてくるように見える。秋からの展開に、ヨーロッパを代表する名門歌劇場ならではの伝統と斬新なサプライズあふれる企画力を期待していきたい。
コメントを残す
今日は、グッド・フライデー。イースター休暇の前、チューリッヒ歌劇場の来シーズンの演目が先日発表された。
郵便でも送られてくるが、歌劇場のクロークの中央のテーブルいっぱいに分厚いプログラムが誇らしげに積み上げられているのを見ると、やはり1冊持ち帰ってくる。
プルミエは、オペラ9本、バレエ3本。
9月22日、ベルント・アロイス・ツィンマーマンBernd Alois Zimmermann のオペラ「兵士たち DIE SOLDATEN」で幕を開ける。
バレエでは、ドイツの革命家にして劇作家 ゲオルク・ビューヒナー Karl Georg Büchnerの生誕200年を祝し、「ヴォイツェック WOYZECK」をクリスチャン・シュピュックChristian Spuckの振り付けで、10月12日より上演する。
「ファウスト FAUST」、オスカーワイルドの短編「カンタヴィルの亡霊 DAS GESPENST VON CANTERVILLE」と続き、1814年に難航の末に初演されたベートーベンの唯一のオペラ「フィデリオ FIDELIO」が、12月8日に登場。シーズンきっての話題作で、クリスマスをはさみ、オペラの季節のピークがフェスティブに華やぐ。
昨年の夏。歌劇場の前で、ペレイラ、ガッティ、シュッペルリの3人が振り向きながら、「さよなら」と手を振っているポスターを見たときは、「ほんとうに、変わってしまうんだ」と一抹の寂しさとともにショックを受けたものだ。周囲のオペラ座サポートメンバーも、「一体どうなってしまうのかわかりません」とノーコメント状態だったが、ペレイラから引き継いだ総裁アンドレアス・ホモキAndreas Homokiの評価は上演ごとに高まり、確実にファンを醸成している。チューリッヒらしい挑戦的な異色作を打ち出しながら、再演のなかにも珠玉が多く光り、2期目のホモキのリードに期待される。
コメントを残す
初めて、チューリッヒ歌劇場でオペラを観たのは、5年ほど前になる。それは、オペラ座サポート・メンバーの方からいただいた切符だった。メンバーや、年間を通じて同じ席を押さえている歌劇場ファンの方たちは、例えば、旅行などで都合がつかなくなった場合、その席を誰か知り合いに譲ることが多い。
「ネルロ・サンティNello Santi をご存知? もし、このオペラがつまらなくても、サンティの指揮をご覧になるだけでも、十分に価値があると思います」。
オーケストラ・ピットのすぐ後ろ。一列目の中央。
今まで見たことのない、どこか超人的な風貌、威厳。大きな身体が、舞台の袖から、ゆっくりゆっくりと歩み指揮台に立って振り向くと、「マエストロ!!」の声が客席のあちらこちら響き渡り、拍手が湧き上がる。
私の目の前に、サンティの顔があった。
1931年、イタリア生まれ。78歳。彼に、老熟、のような形容は、まったくあてはまらない。力強く繊細でリリカルな音楽を作る、現代屈指の世界的な指揮者だ。
チューリッヒ歌劇場では、1958年に初めて指揮者を務めているが、時代とともに音楽監督が変遷して行っても、サンティは、この歌劇場を代表する誇り高き存在。日本では、N響と定期的に公演を持っている。
サンティが創り出す音楽とにじみ出る至上のオーラの魔法にかかり、私はこの夜、あまりにも大きな衝撃を受けた。
そのマエストロ、サンティが、チューリッヒ歌劇場の今年のオペラのなかでも、ひときわ注目度を上げた作品のひとつ、ジョアキーノ・ロッシーニ Gioachino Rossiniの「セビリアの理髪師 Il barbiere di Siviglia」を振った。
今回の「セビリアの理髪師」は、ペレイラ総裁の大胆なアイデアで、スイスのイタリア語圏テッシーン出身のスター建築家、マリオ・ボッタ Mario Bottaが舞台美術を担当。演出は、辣腕 チェザーレ・リェーヴィ Cesare Lievi。ユニークなコラボだが、歌手も大物ベテラン、若手実力派と、まさに役者が揃ったプロダクションだ。
時は19世紀初め。スペイン南部のセビリア。
街の何でも屋の理髪師フィガロが、医者である後見人に見張られている若い美女と伯爵の恋を、実らせる。後見人の謀略やサディスティックなまでの執拗な妨害を、フィガロのあの手この手、機知に富んだ名案で切り抜け、二人はめでたく結婚する、というオッペン・ブッファ。風刺のきいた喜劇として知られる。
フィガロのマッシモ・カバレッティ Massimo Cavallettiのとことん明るいスター性。
籠の鳥ロジーナの財産を狙って結婚をたくらむ医者バルトロに、カルロス・ショソンCarlos Chausson。彼に取り入る音楽教師バジリオに、ものの見事に凄みの効いた偽善者の悪役を演じたルッジェーロ・レイモンディ Ruggero Raimondi。この二人の大ベテランの歌と演技が、ロッシーニの上質な喜劇に、燻銀のような光彩を放ち風格をもたらす。
演出家リェーヴィが語る。「私は、この物語がいかに不条理であるか表現しようと試みました。人生は、不条理です。テーマは、愛。それも、かなり特殊な愛です」。
身分を偽りロジーナの愛を確かめようとする伯爵アルマヴィーヴァに、マリオ・ツェフィーリ Mario Zeffiri。兵隊になったり、音楽教師に化けたり、変幻自在に変装しては、愛するロジーナの前に現れる。
令嬢ロジーナは、この舞台でチューリッヒ歌劇場にデビューしたメゾ・ソプラノのセレーナ・マルフィ Serena Malfi。キュートで頭の回転の早い現代っ子。後見人の意地悪を巧みにかわし、二人の縁を取り持とうとするフィガロの知恵さえ先回りしてしまう。ちょっと気まぐれだが、誠実。貧乏学生に扮した伯爵アルマヴィーヴァを愛する。
リェーヴィは続ける。「アルマヴィーヴァは、恋に落ちています。彼は虚構を楽しみ、多情な冒険を愛し、女性を所有することを愛しているのです。しかし、彼が、本当に彼女を愛しているのか。それは、私にはわかりません」。
衣装デザイナーと相談し、コスチュームを大きく2つのパーツに分けたと言う。とても年老いた人々。そして、若い人々。
この喜劇は、世代や価値観の対立、貴族と庶民という身分の対立が基盤にあるが、衣装によってもこのコンフリクションを表現しようとした。
理髪師フィガロは、これほどの頭脳明晰をもってすれば、あの時代いかようにも出世する機会があったはずだが、どうも、その手の話には無頓着であることを気質としている。軽妙な演技と歌を楽しませながら誰よりも走り回って活躍するものの、登場人物全員のなかで最も冷静な視線を持っている。庶民的な親しみと巧妙さに好感が持てるのは、カバレッティのキャラクターによるところも大きい。
また、いつもくしゃみをしている女中ベルタ役のレベッカ・オルヴェラ Rebeca Olveraは、美しいソプラノでアリアを聴かせる。老けた女中で「老いた人々」の側に属しながら、飄々としたうまいおとぼけが、ストーリー全体のなかで洒落たスパイスになっている。
さて、マリオ・ボッタのステージ・デザインは、観客にもメディアにも、賛否両論。私は、いかにもこの歌劇場らしい斬新な挑戦で面白いと思ったが、新聞の批評はかなり辛口だった。
ボッタは、チューリッヒの街そのものが興味深いターゲットだと語る。
「チューリッヒは、現代アートの影響を強く受けている大変モダンな街です。バウハウスの時代以降、グラフィック・アートと近代アートが、この街に様々な美意識をもたらしましたが、私たちは、20世紀セカンド・パートの芸術の世界に『セビリアの理髪師』を運んできます」。
この歌劇場のバレエのステージを2度デザインしているが、オペラは初めてだ。
2つに重なったメタル・グレイの4つのキュービックが、ストーリーとともに舞台を稼働し、光を変えたり、画面にムービーや鏡が現れたりする。
また、何でも屋の理髪師フィガロが持っているトランクは、どこでも開店してしまう彼のお店であり、ハサミやカツラや手足、おまけに何故か、首がぐんぐん伸びるキリンまで登場する。15と数字が大きく書かれているが、彼がお店を開けたところは15番地、ということらしい。
何だか、「ふうてんの寅さん」を思い出した。
ボッタの話に戻ろう。
「建築と舞台の間には、大きな違いがあります。建築は、常にユニークな空間や場を創造します。舞台は、これとはまったく違い、部屋をデザインすることがタスクではありません。しかし、人々に夢を見てもらわなければなりません。観客の想像力を演じることが、大きな役割なのです」。
カーテン・コールが続き、ネルロ・サンティも舞台に上がって来る。
オーケストラのすべての楽器を演奏できると聞いたが、今回は、囁くようなチェンバロを奏でた。
サンティが表現した「ロッシーニ・クレッシェンド」は、ロッシーニがこの喜劇を上質に仕立てたように、笑いも諧謔も風刺も音で表現する、詩的で格調高い作品となった。
マエストロは、誰よりも深く長く頭を下げ、やがて穏やかな笑みを浮かべて、ゆっくりと客席を見渡している。
Stage Photo: Opernhaus Zürich/ Suzanne Schwiertz
コメントを残す
オペラを観に行くとき。しかもいい席が取れている場合ならなおさら、前日、できるだけ睡眠をとるようにする。
チューリッヒ歌劇場のように、1100席という小さな空間では、舞台との距離も遠くない。よほど天井に近い席でなければ、この劇場は音響がいいので、揃いも揃った精鋭の生身の人間の迫力を受け止めるには、こちらもまた、それなりの体力がいるというものだ。
でも、元気と時間に余裕があるときにホームページを覗いて、まだ空いていれば手頃な席を取り、ぶらっと行くというフットワークも、私は結構気に入っている。初日ではなく、プレミアム席でないならば、それほど頑張ったお洒落をしなくても、周囲の方にも失礼ではない。自分で心地良ければそれでいい。そんなふうに、肩に力を入れないでオペラにワープするみたいに、非日常の世界に滑り込んでゆく。
日本から親しい友人がやって来た。芝居通、歌舞伎通だ。もちろん、今回の旅のお目当てのひとつは、オペラ。ラッキーなことに、彼女がやってくる頃、ちょうどビゼーGeorges Bizet の「真珠採りLes pêcheurs de perles」を上演していた。
フランスの芸術家の登竜門「ローマ賞」を受賞し、イタリアからパリへ戻って来たビゼー。25歳のときに書かれた作品だ。それから約10年、「カルメンCarmen」が初演されると間もなく、36歳という若さで病死してしまう。オペラの世界で重要な地位を確立して、これから歴史を変えたであろう才能。もしもその先「カルメン」を超える作品が作られていたらどんなに素晴らしかっただろうと思う。
決して寡作ではないものの、オペラで知られる作品の数が少ないためもあってか、作品の大きさや構成など、「真珠採り」は「カルメン」とよく対比される。
「真珠採り」はビゼーの死後、かなりドラマチックに変遷し、いくつものユニークな演出によって作品がディテールを変えつつ発展し続けているといわれる。
指揮者のカルロ・リッツィCarlo Rizzi は、「カルメン」は、もっと肉感的で血を騒がせるような生命力にあふれたダイナミックなオペラだとしながら、こう語る。
「ビゼーは、『真珠採り』を書いた時代、まだ本格的にデビューしていませんでした。若かったし、その若さゆえの純粋さや透明感が、この作品にあるのだと思います。ストーリーは、シンプルでわかりやすく、いずれの曲も、とにかくメロディーがクリアで大変に美しい」。
19世紀後半のフランス。イタリアオペラの人気がまだまだ優勢であったものの、「フランスのオペラ」が登場し、オペラ界に新しい潮流が生まれてきたエポックだった。
そのような時代背景が、ストーリーに影響を与えているのか。
演出家は、演劇性の高さでことに定評のある、イェンス-ダニエル・ヘルツォーク Jens-Daniel Herzog。やや社会性の強い捉え方をしている。
チューリッヒ歌劇場の舞台美術や照明は、観客をびっくりさせるような仕掛けが組み込まれていることが多いが、今回は、ストーリーのわかりやすさを受けてか、複雑な構造はなかった。
古代のセイロンの浜辺。
舞台は、あまり動かない。初めから、3層に組まれている。
前出のヘルツォークによると、「まず一番下。真珠採りたちが並んでいますが、ここが労働者の象徴。真ん中が、中流階級。そして、荒れ果てた僧院のある一番上の層が、この『真珠採り』の世界のシステムのトップです」。
そのような構成をより明確にするためにも、真珠採りたちは、舞台の上にとどまる。
何十人もの真珠採りが一斉にオレンジ色の手袋をはめた手を動かしながら、終始そこにいるという、塊りの力の奇妙さを引きずっていく。
真珠採りの新しい頭に選ばれたゾルガに、バリトンのフランコ・ポンポーニ Franco Pomponi。
その旧友で、かつては、ゾルガと同じ女性を愛し対立した ナディールに、テノールのハビエル・カマレーナJavier Camarena。
ナディールの恋人だったが、この浜辺に真珠採りたちの安全を祈願するために遣わされる尼僧レイラは、ソプラノのマリン・ハルテリウス Malin Hartelius。
レイラを連れてくるバラモンの高僧ヌーラバットは、バスのパヴェル・ダニルクPavel Daniluk。
尼僧レイラは、ゾルガから一生ヴェールを取らず、真珠採りの安全を祈り続けること、処女であることを誓わされる。
しかし、「あっ、あの人だ」とお互いに気づいてしまったレイラとナディール。
アリア、二重唱、三重唱と、いくつもの有名な曲が次々と歌われる。
旧友との再会、もう争いの種になる恋人は目の前にいないのだからと友情を讃える、ハビエル・カマレーナとフランコ・ポンポーニの二重唱「黄金と花に飾られた神聖な寺院の奥に Au fond du temple saint」は、実に美しい。
一番良く知られているのは、何と言っても ナディールがレイラを想って歌う「耳に残る君の歌声 Je crois entendre encora」。ハビエル・カマレーナは、チューリッヒ歌劇場でも大人気の歌手だが、この歌の最初のフレーズが深く切なく流れると、何ともロマンティックで、ふ~っとどこかに連れて行かれるような柔らかさに包み込まれる。メキシコの方だが、ちょっと東洋的な雰囲気もあり、長く村を離れていた冒険好きな青年の自由を演じ、レイラに熱烈に愛を語る。
尼僧レイラのソプラノは、神々しささえ感じる。指揮者のカルロ・リッツィが何度も強調している旋律の透明感に高貴が織り込まれる。
特に、ヴェールを被って舞台の最上から響き渡る1幕目の最後、「ブラーマの神よ!Brahma, divin Brahma!」から続くアリア「空にさえぎるものなく Dans le ciel sansa voiles」が、素晴らしい。
レイラとナディールが再び愛し合うようになったことは、見張りの教徒からヌーラバットにすぐに伝わり、二人は処刑されることになる。
ナディールを助けて欲しいとゾルガに懇願するレイラ。尼僧が実はレイラだったと知った時に、ゾルガは、愛を告白するが、レイラの気持ちを変えることはできない。嫉妬のあまり、ズルガは二人に死刑を宣告してしまう。
レイラは、「殺されるなら、これを母に届けて欲しい」と真珠の首飾りを差し出す。それは、ゾルガが逃亡していた時に、命がけで彼を助けてくれた少女に渡したもの。
ゾルガは、村に火を放ち、村人が混乱している間に二人を逃がすことにするが、そのシーンの前に歌われる、やはり有名な三重唱、「聖い光よ、すばらしい抱擁よ O lumiere sainte」となると、この3人の歌声が、波のように押し寄せてきては引き返すという繰り返しで、歌劇場にはドラマティックな海が洋々と満ちてゆく。
終盤、村人たちに殺されるゾルガ。光の中へ消えてゆくナディールとレイラ。権力は民衆に倒され、信仰に戸惑いながらも、最後に愛が一番輝くという、物語。ストーリーが理解しやすいので一生懸命字幕を追うこともなく、美しく豊かな歌声をゆっくり楽しむことができる。
その夜はずっと、アリアの旋律が耳の奥でこだましていた。
Photo: © Suzanne Schwiertz