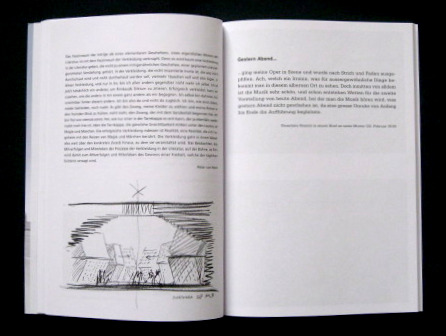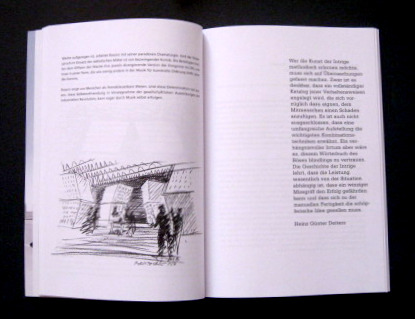初めて、チューリッヒ歌劇場でオペラを観たのは、5年ほど前になる。それは、オペラ座サポート・メンバーの方からいただいた切符だった。メンバーや、年間を通じて同じ席を押さえている歌劇場ファンの方たちは、例えば、旅行などで都合がつかなくなった場合、その席を誰か知り合いに譲ることが多い。
「ネルロ・サンティNello Santi をご存知? もし、このオペラがつまらなくても、サンティの指揮をご覧になるだけでも、十分に価値があると思います」。
オーケストラ・ピットのすぐ後ろ。一列目の中央。
今まで見たことのない、どこか超人的な風貌、威厳。大きな身体が、舞台の袖から、ゆっくりゆっくりと歩み指揮台に立って振り向くと、「マエストロ!!」の声が客席のあちらこちら響き渡り、拍手が湧き上がる。
私の目の前に、サンティの顔があった。
1931年、イタリア生まれ。78歳。彼に、老熟、のような形容は、まったくあてはまらない。力強く繊細でリリカルな音楽を作る、現代屈指の世界的な指揮者だ。
チューリッヒ歌劇場では、1958年に初めて指揮者を務めているが、時代とともに音楽監督が変遷して行っても、サンティは、この歌劇場を代表する誇り高き存在。日本では、N響と定期的に公演を持っている。
サンティが創り出す音楽とにじみ出る至上のオーラの魔法にかかり、私はこの夜、あまりにも大きな衝撃を受けた。
そのマエストロ、サンティが、チューリッヒ歌劇場の今年のオペラのなかでも、ひときわ注目度を上げた作品のひとつ、ジョアキーノ・ロッシーニ Gioachino Rossiniの「セビリアの理髪師 Il barbiere di Siviglia」を振った。
今回の「セビリアの理髪師」は、ペレイラ総裁の大胆なアイデアで、スイスのイタリア語圏テッシーン出身のスター建築家、マリオ・ボッタ Mario Bottaが舞台美術を担当。演出は、辣腕 チェザーレ・リェーヴィ Cesare Lievi。ユニークなコラボだが、歌手も大物ベテラン、若手実力派と、まさに役者が揃ったプロダクションだ。
時は19世紀初め。スペイン南部のセビリア。
街の何でも屋の理髪師フィガロが、医者である後見人に見張られている若い美女と伯爵の恋を、実らせる。後見人の謀略やサディスティックなまでの執拗な妨害を、フィガロのあの手この手、機知に富んだ名案で切り抜け、二人はめでたく結婚する、というオッペン・ブッファ。風刺のきいた喜劇として知られる。
フィガロのマッシモ・カバレッティ Massimo Cavallettiのとことん明るいスター性。
籠の鳥ロジーナの財産を狙って結婚をたくらむ医者バルトロに、カルロス・ショソンCarlos Chausson。彼に取り入る音楽教師バジリオに、ものの見事に凄みの効いた偽善者の悪役を演じたルッジェーロ・レイモンディ Ruggero Raimondi。この二人の大ベテランの歌と演技が、ロッシーニの上質な喜劇に、燻銀のような光彩を放ち風格をもたらす。
演出家リェーヴィが語る。「私は、この物語がいかに不条理であるか表現しようと試みました。人生は、不条理です。テーマは、愛。それも、かなり特殊な愛です」。
身分を偽りロジーナの愛を確かめようとする伯爵アルマヴィーヴァに、マリオ・ツェフィーリ Mario Zeffiri。兵隊になったり、音楽教師に化けたり、変幻自在に変装しては、愛するロジーナの前に現れる。
令嬢ロジーナは、この舞台でチューリッヒ歌劇場にデビューしたメゾ・ソプラノのセレーナ・マルフィ Serena Malfi。キュートで頭の回転の早い現代っ子。後見人の意地悪を巧みにかわし、二人の縁を取り持とうとするフィガロの知恵さえ先回りしてしまう。ちょっと気まぐれだが、誠実。貧乏学生に扮した伯爵アルマヴィーヴァを愛する。
リェーヴィは続ける。「アルマヴィーヴァは、恋に落ちています。彼は虚構を楽しみ、多情な冒険を愛し、女性を所有することを愛しているのです。しかし、彼が、本当に彼女を愛しているのか。それは、私にはわかりません」。
衣装デザイナーと相談し、コスチュームを大きく2つのパーツに分けたと言う。とても年老いた人々。そして、若い人々。
この喜劇は、世代や価値観の対立、貴族と庶民という身分の対立が基盤にあるが、衣装によってもこのコンフリクションを表現しようとした。
理髪師フィガロは、これほどの頭脳明晰をもってすれば、あの時代いかようにも出世する機会があったはずだが、どうも、その手の話には無頓着であることを気質としている。軽妙な演技と歌を楽しませながら誰よりも走り回って活躍するものの、登場人物全員のなかで最も冷静な視線を持っている。庶民的な親しみと巧妙さに好感が持てるのは、カバレッティのキャラクターによるところも大きい。
また、いつもくしゃみをしている女中ベルタ役のレベッカ・オルヴェラ Rebeca Olveraは、美しいソプラノでアリアを聴かせる。老けた女中で「老いた人々」の側に属しながら、飄々としたうまいおとぼけが、ストーリー全体のなかで洒落たスパイスになっている。
さて、マリオ・ボッタのステージ・デザインは、観客にもメディアにも、賛否両論。私は、いかにもこの歌劇場らしい斬新な挑戦で面白いと思ったが、新聞の批評はかなり辛口だった。
ボッタは、チューリッヒの街そのものが興味深いターゲットだと語る。
「チューリッヒは、現代アートの影響を強く受けている大変モダンな街です。バウハウスの時代以降、グラフィック・アートと近代アートが、この街に様々な美意識をもたらしましたが、私たちは、20世紀セカンド・パートの芸術の世界に『セビリアの理髪師』を運んできます」。
この歌劇場のバレエのステージを2度デザインしているが、オペラは初めてだ。
2つに重なったメタル・グレイの4つのキュービックが、ストーリーとともに舞台を稼働し、光を変えたり、画面にムービーや鏡が現れたりする。
また、何でも屋の理髪師フィガロが持っているトランクは、どこでも開店してしまう彼のお店であり、ハサミやカツラや手足、おまけに何故か、首がぐんぐん伸びるキリンまで登場する。15と数字が大きく書かれているが、彼がお店を開けたところは15番地、ということらしい。
何だか、「ふうてんの寅さん」を思い出した。
ボッタの話に戻ろう。
「建築と舞台の間には、大きな違いがあります。建築は、常にユニークな空間や場を創造します。舞台は、これとはまったく違い、部屋をデザインすることがタスクではありません。しかし、人々に夢を見てもらわなければなりません。観客の想像力を演じることが、大きな役割なのです」。
カーテン・コールが続き、ネルロ・サンティも舞台に上がって来る。
オーケストラのすべての楽器を演奏できると聞いたが、今回は、囁くようなチェンバロを奏でた。
サンティが表現した「ロッシーニ・クレッシェンド」は、ロッシーニがこの喜劇を上質に仕立てたように、笑いも諧謔も風刺も音で表現する、詩的で格調高い作品となった。
マエストロは、誰よりも深く長く頭を下げ、やがて穏やかな笑みを浮かべて、ゆっくりと客席を見渡している。
Stage Photo: Opernhaus Zürich/ Suzanne Schwiertz